星戦士スターセイバー
「英雄の代償」
「流星君が家出した?」
そのよく知っている名前を聞いて、少女の目が丸く見開かれる。
瞳の色は薄く透き通っている。異国の血を感じさせる髪とともに彼女の容姿を彩っていた。
「しかも、セイバーブレスを置いて?」
困惑する少女であったが、自分より狼狽している者を見ると急に頭が冷えてきた。
「……ねぇ、アック。まずは落ち着いて。詳しく聞かせてちょうだい」
アメリカ生まれの祖母から生まれた、日本人の父。来日するまでは、まだ忍者が実在すると思っていたフランス人の母。そんな両親を持つのが瀬戸瀬里奈という少女だ。
11歳という年齢とは思えないほどに、大人びた態度で続きを促す。
「あわわわわ」
アックと呼ばれた、見た目も動きもフンワリした物体はしばらくオロオロしていた。
「最近、様子がおかしかったですよ」
ようやく冷静になってきたのか。最初、よく聞き取れなかった彼の言葉もずいぶんクリアに聞こえるようになってきた。
「ブレス置いてかれたらボクじゃ追いかけられないです!」
「う~ん、確かに昨日も学校で声をかけようとしたら避けられたんだよね」
「ですぅ。家でも何か考え込んでるです」
流星の様子がおかしい理由、思い当たる点はいくつかある。
「やっぱり、あれかなぁ」
その中の一つを思い出す。あれは確かに瀬里奈にも衝撃的な出来事だった。
「だったら、私がなんとかしないと」
瀬里奈の脳裏に浮かぶのは、一人の女性の悲しげな笑顔だった。
それは、数日前のこと。瀬里奈達が人知れず行っている仕事の後の話。
「今日の流星君、動きが悪かったなぁ。何があったんだろ?」
いつものように人気のない場所に移動する瀬里奈。
背中には深紅のマント。体のサイズから子どもと分かるものの、ゴーグルで隠された彼女の表情は外からはうかがい知れない。
運命の日。天から降る狂った凶星、フィアマスによって滅ぼされる。そんな未来を変えるべく奮闘する幼き英雄達。
その一人が、瀬里奈。またの名を、レッドセイバー。
「おつかれさま。今日も大変だったね」
思わず、瀬里奈はびくりと体を震わせる。
いつものように人気のない場所で変身解除をしようとしたら一人の男が声をかけてきたのだ。
マスコミとか、いつもだったらうまくやり過ごすところだ。もう慣れっこである。
しかし、彼の様子は違っていた。セイバーに向けられる、好奇、尊敬、そして畏怖。それのどれとも違った穏やかで優しい瞳だった。
「レッドに声をかけるならあたしに声をかけてからにしてくれだわ」
ふわふわと瀬里奈の周囲に浮かんでいた、ぬいぐるみのような物体が彼と彼女の間に入った。
マネージャー気取りなヒーチャに苦笑いを浮かべつつ、視線を男性から外さない瀬里奈。
「ヒーチャ、僕のこと忘れた?」
「ふえ?」
ヒーチャは目を真ん丸にして瀬里奈を見る。そんなヒーチャに瀬里奈は苦笑いを浮かべた。
(そんな顔されても、あなたが知らないのに私がわかるわけないでしょ)
彼は、小さく息を吐いた。
「瀬里奈さん、でいいよね? ちょっと話をしたいんだけど」
本名まで知られている。あまり表には出てこないヒーチャのことも馴染みのように話す。
これは本物だ、と瀬里奈は思った。
彼はセイバーに用があるわけではない。『セイバーに変身している瀬戸瀬里奈』に用件があるのだ。その事実に、緊張が沸き上がった。
返信解除のために、ブレスのボタンを押す彼女の手が震えている。そんな様子も、穏やかな視線で彼は見つめていた。
いつでも逃げ出せるよう、周囲を警戒しつつ彼の導きに従う瀬里奈。しかし、彼の口から衝撃的な話が飛び出し、いつしか緊張は解けてしまった。
ちがう緊迫感が彼女を襲ったからだ。
「10年前」
「そう、10年前。僕らは確かに戦っていた。セイバーとして」
10年前、地球は今とは別の侵略者に襲われていた。その名は妖魔王。
当時、生まれたばかりの瀬里奈の記憶にないのは当たり前。しかし、問題はそこではない。それほど大きな戦いを、大人達は誰も語っていないのだ。
歴史から、消え去ってしまっている。
「君は知らなくて当然なんだけど、ヒーチャも?」
テラのやつ、徹底してるよなと笑う彼の顔が先ほどより幼く見えたのは気のせいではない。
彼の名は布良昴。10年前の大戦、彼も瀬里奈のようにセイバーの衣装を身にまとっていた。
「人の記憶はセイバーに関することだけ消える。そう、テラが最後に言っていたよ」
昔を懐かしむその笑顔は、しかし、どこか苦しげだった。
「あ、そうか。テラも僕達が勝手につけた名前だった」
「ああ」
先ほどから彼の言っていたテラが誰か見当もつかなかった瀬里奈であったが、その言葉で合点がいった。勝手につけた名前、で思い当たるのは一人だ。
——この星を頼みます。星の護り手よ。
ヒーチャを通じて、瀬里奈に戦うことを依頼してきた地球の精霊。
彼女には自分から名乗る名前がない。だから、流星が彼女と似ているというゲームのお姫様から名前を付けて瀬里奈達は呼んでいた。
「私達はアリシアと呼んでいます」
彼女は人に付けられた名前を呼ぶと喜ぶのだ。瀬里奈はそこで初めて、昴の前に柔らかな顔を見せた。
「へぇ~、彼女とも久々に会いたいなぁ」
昴は残念そうに息を吐いた。
「テラには会いにいけないからね。私達」
背後から声がして振り返った。
「でも、私はヒーチャと会えただけでも満足だよ?」
本当に嬉しそうに微笑む女性がそこにいた。周囲の白い壁の印象も加えて、瀬里奈は彼女の線の細さが少し気になる。
しかし、近寄ってくる足取りは思いのほか力強かった。
「久しぶり! あなたが忘れていても私は嬉しいよ」
ヒーチャは少し戸惑っていた。彼女のことは、やはり知らない。しかし、自然と笑顔がこぼれる。
まるで、記憶がどこかにあるように。
「今のヒーチャ、紅色なんだよ。姉さんと一緒だった時は黄色だったのに」
「えー、そんなのださいだわ」
「そんなことないわよ。あの時のあなた、最高に可愛かったわ。何度試しても写真に写らないから残すのは断念したんだけどね」
流星にすら最初心を開かなかったヒーチャが笑っている。その光景に、瀬里奈はしばらく言葉を失っていた。
「せりなちゃーん、助けてだわっ」
瀬里奈が再び口を開いたのは、ヒーチャが彼女にぎゅうぎゅうと抱きしめられて悲鳴をあげているときだった。
「それじゃあ、あなたも」
「ああ、ごめんなさい。興奮しすぎていたわ」
あらためて瀬里奈と向き合う彼女。その時、ある違和感を瀬里奈は感じた。
「私の名前は布良織姫。よろしくね、後輩さん」
瀬里奈を見ているようで、焦点が定まっていない織姫の瞳。
――今のヒーチャ、紅色なんだよ。
昴のおかしな台詞も、それなら納得がいった。
検査入院している織姫の病室。織姫はベットに腰掛け、気を失っているヒーチャを撫でていた。
今は壁に体重を預けている昴に促されるまま、瀬里奈は椅子に腰掛けていた。
「私の目? うん、見えてないよ」
恐る恐る訪ねてみると、非常にあっけなく織姫は答えた。
「いつからですか?」
「……分かってて聞いてるよね、あなた」
少しだけ鋭い口調で彼女は言う。その迫力に、気圧される。額に冷たいものを感じたとき、織姫はくすりと微笑んだ。
「ごめん、ちょっと意地悪した」
「大人げないよ、姉さん。いじめて楽しい?」
ちょっとだけね、と織姫は子供っぽく笑った。
「あなたが想像している通り、かな」
それは最終決戦。敵の本拠地に乗り込んで彼らは戦った。あと一歩で戦いが終わる。その時、妖魔王の一撃が彼女をとらえたのだ。
その強烈な閃光は織姫の目から光を奪っていった。
「私は昴と違って少しだけ力が残ってるから、日常生活に不便はないけどね」
確かに、織姫の歩みはしっかりとしていた。周囲の様子を感じ取れるようだ。
「だから、ね。うん、私は良いんだ」
織姫の表情が歪む。苦しげに、悲しげに。
「瀬里奈ちゃん」
「は、はい」
重い空気に背筋が伸びる。そんな瀬里奈の雰囲気を感じ取って、織姫は微笑んだ。
「蒼い子のこと、教えてくれる?」
彼女がブルーセイバー、矢崎流星のことを聞いているのだとすぐに分かった。
一通り話終わると、織姫は立ち上がった。
その振動でやっと目が覚めたヒーチャは彼女の手を離れて、周囲をきょろきょろと見渡している。
開いた窓から入ってくる風。心地よいそれは織姫の髪を撫でていった。
「そっか、やっぱり」
「やっぱり?」
「お兄ちゃんと似ているなって」
織姫はゆっくりと自身の兄、北斗について語り出した。
人が傷つく事を恐れ、自分が受ける傷を代償に世界を守った戦士。そして、最後の戦いから未だに帰ってこない勇者の話を。
「僕は似ていないと思うけど」
昴が織姫の話を遮る。あまり聞きたくない話を止めようとしている、瀬里奈はそんな空気を感じ取った。
「私が言っているのは、根元のところ。ほら、あの子も自分よりも他の人、優先してそうだったでしょ」
「……まぁ、否定しないけど」
彼女らは瀬里奈と会う前に、流星とも接触している。だから、瀬里奈の名前も最初から知っていたのだ。
「流星君にも話したんですか? お兄さんのこと」
織姫は、瀬里奈の言葉に棘を感じ取った。
「……その言い方、少し非難している?」
「分かりますか?」
「分かるわよ。そうよ、話しちゃいました」
瀬里奈の視線が、さらに鋭くなる。
彼女の知っている流星という少年は『誰かが傷つく話』が大嫌いなのだ。
たとえ自分とは関係のないうえに取り戻せない過去のことだって、何もできない自分を悔やんでしまう。
それが分かっている瀬里奈は自分の動揺よりも、彼の事が気がかりだった。
「それにしても瀬里奈ちゃんは落ち着いているわね。どっちが大人なのか分かんなくなっちゃう」
「姉さんがいつまでたっても子どもなんだよ。中身、10年経っても変わらないんだから」
「昴、お姉ちゃん怒らないからこっちきなさい」
昴は一瞬で姿を消していた。台詞だけ残して、病室を去っていったのだろう。織姫もすでに昴の後を軽やかな足取りで追いかけていく。
本当に、目のハンデを感じさせない動きだ。
一人残された瀬里奈は大きく息を吐く。
(二人とも、仲良く子どもってことね)
そんな出会いを思い出すと、瀬里奈は背筋が寒くなった。
「怖い、よね。私だって怖くなったもん」
二人とも「後悔はない」と言っていた。しかし、本当にそうだろうか。
光を失い、愛する家族を失う代償を支払って手に入れたのは、英雄としての賞賛だけ。それも自分ではなく、「セイバー」に向けられたもの。
「それすらもなくしてしまうなんて、ね」
おそらく、自分達の戦いが終わった後もアリシアは同じ様に処理するのだろう。それならば、たとえ勝ったとして自分達は何の為に戦っているのだろう。
「世界の平和のため。かっこいいね」
自虐的に笑うと、自分のセイバーブレスを見つめた。
それでも確かに、守りたいものはある。それを、信じるしかない。
――蒼い子を助けてあげて。絶対に無理するから。
「そんなの分かってる」
付き合いは短いが、信頼する仲間だ。
「相談、してくれればいいのに」
流星はそれほど自分を信頼していないのかと思うと、気が滅入る。瀬里奈は初対面から彼に気を許しているというのに。
「アック。手分けして探しに行こう。大丈夫、流星君はきっと見つかるよ」
「はいです!」
今度、時間をとって一緒に話し合ってみよう。瀬里奈はそう決心する。
意識の片隅に追いやって考えないでいた、この戦いの意味を。
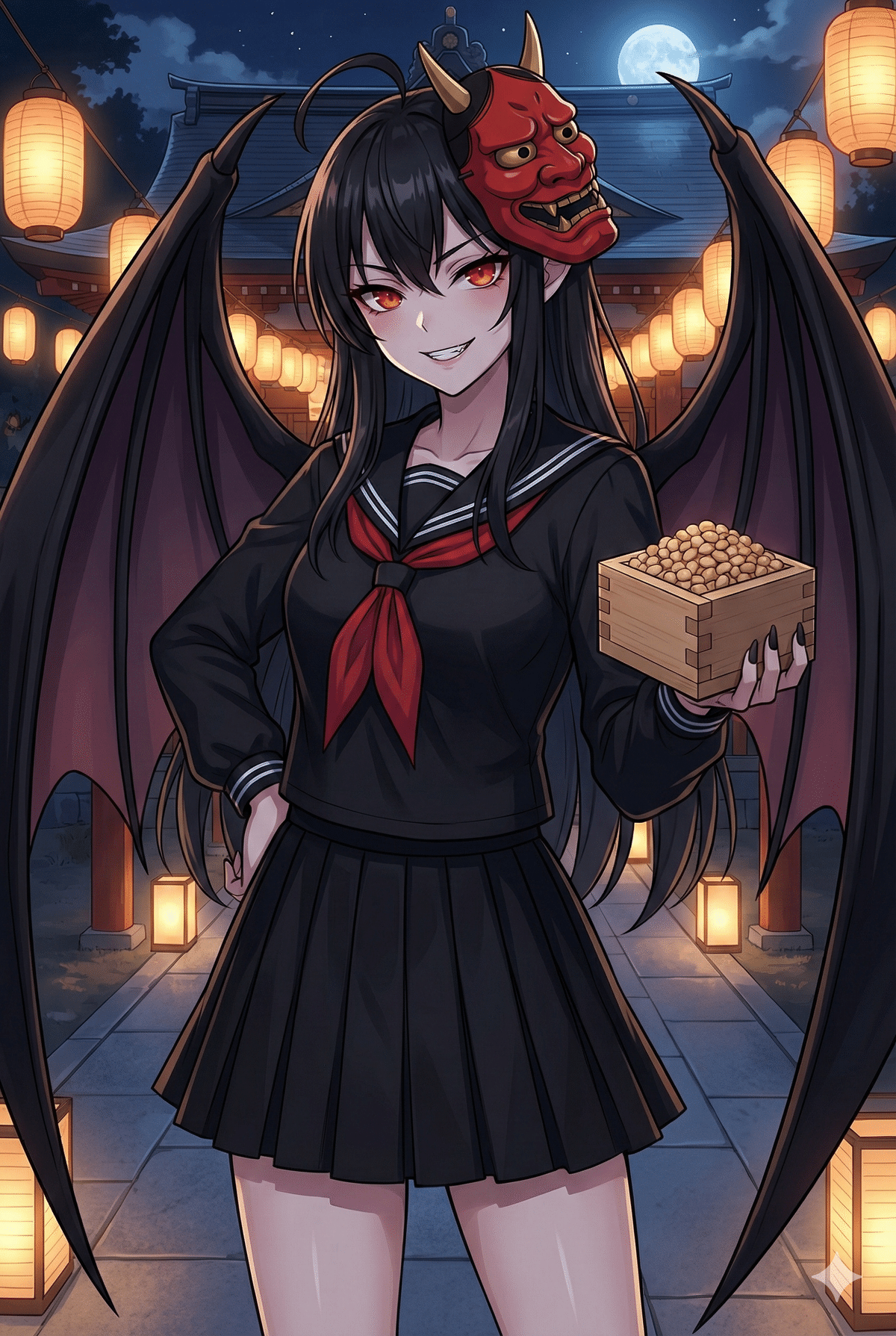

0 件のコメント:
コメントを投稿