『四番、ファースト、瀬川くん』
その場内アナウンスが耳に入ったとき、大海ひろみは思わず身震いした。
出場する、とは前から聞いていた。だからこそ、監督に無理言って休みをもらい、偵察すらいらぬ小さな大会まで足を運んだのだ。
そして、今。距離はあるが打席に向かう姿も目の前にある。
(ああ、ほんとうに)
それでも、自分以外の誰かが彼の存在を認識し、その名を口にしているという事実は感慨深いものだった。
「あれが瀬川陸、か」
大海の隣で、暇そうに足をぶらつかせていた少年も、そのアナウンスで試合に注意を戻した。
「聞いてはいたけど、ちっこいな」
「岸田先輩……」
大海は文句でも言ってやろうと思い、しかし、自分は言う立場ではないと思い直して押し黙った。
そんな彼を見て、大海の一つ上の学年である岸田有ゆうは大きく息を吐いた。
「おまえが気にする奴ってのを見てみたくて来たけど……ほんとに、そこまでの選手なのかね」
有は思う。隣にいる佐原大海は紛れもなく天才だ、と。春の全国大会の活躍を見たものであれば、野球を知らなくても皆がそう思うだろう。それだけの選手だ。
そんな彼に中学時代の話をさせたことがある。男子高校生らしい、浮ついた話を期待した上級生が一様に顔をしかめたのを覚えている。
なにせ、彼が語ったのは中学時代の同級生の武勇伝だ。きょとんとした聴衆の顔なんて目に入らない。出会いから別れまでのドラマティック・ストーリーが展開された。目の輝きは、まさに恋する少女に似ている。お酒を飲まずとも酔っている、そんな様子だった。
その主役だったのが、眼前の小さな四番打者。瀬川陸である。
「まぁ、見ててくださいよ」
ふてくされた様子で、大海は有から視線をそらした。いや、そらしたのではない。陸の打席に集中し始めたのだ。
「そりゃ、見るためについて来たんだけどな」
しかし、見れば見るほど迫力の無い打者だと有は思う。対戦相手の投手も、そう思ったのだろう。先程まで浮き足立っていたのに急に落ち着いてきた。
(まぁ、慌てるのは分かるよ。同じ投手だから)
なんせ、相手は今年からの新規参戦。元女子校。ベンチ入りのメンバーは全員で12人。
それなのに、いきなりのバントヒット。そして、初球からいきなり盗塁。さらに二番打者に簡単に送られた。そんなスマートな野球をされるとは思っていなかった投手は完全に焦っていた。
続く三番は、粘りに粘って9球目に四球を選んだ。隙の無い、横綱のような野球だ。
陸への初球。決して遅くない速球で簡単にストライクをとる。打つ気のなかった陸は、全く微動だにせず見送った。こっから立ち直ろう、投手のそんな意思を感じる球だった。
陸はぐるりとバットを回す。大きく背を伸ばしてから、彼は構えをただした。
(あれ?)
そこで、有は違和感を覚えた。先程までの楽な相手だというイメージが急に吹き飛んだのだ。
体の大きさは変わっていない。それなのに。
(大きい)
甲子園球場で見た化け物達。その誰にも劣らぬくらい大きく見えた。それは有の投手としての本能が告げる危機によるものだ。うかつに攻めたらやられる、と脳に訴えかけている。
マウンドにいないというのに、だ。これで対峙していたら、どれほどのものだろうか。
しかし、実際に対戦している投手はそんなあからさまな危険を感じることができていなかった。一球目と同じ、気の抜けた速球。
陸は、それを見逃す選手ではない。
高い音が球場に響く。白球は放物線を描き、球場の一番深いところまで飛んでいった。
スリーランホームラン。
「……なんだ、ありゃ」
ようやく絞り出した有の声はかすれていた。
「あれが、瀬川陸です」
その有の反応を見て、嬉しそうに大海は頷いた。
そこからは、また大海の熱弁が始まった。陸は肘を怪我して断念したが、本当は一緒の高校に来るはずだった。だから、監督も今日の試合を見に来ることを許してくれたと。彼の肘は治っていないけれど、野球部を作りたいと活動する少女に巻き込まれる形で入部した。本当なら、高校野球は諦めるつもりで野球部のない高校に入ったというのに。
「そういうのが陸っぽいというか。本人、嫌がってる感じを出しているのに、いつの間にか、中心にいるんですよ」
きらきらと目を輝かせる大海に、有は少しだけ不安を感じる。
(分かってんのか。そいつが復活したってんなら、かなりの強敵になるんだぞ)
陸の学校は同地区だ。そんな感じで戦えるのか、と有は大海をたしなめたくなる。とは言っても、今の大海には暖簾に腕押しだろう。
(そっか、でも)
有は左手を握りしめる。しっかりと力が入らない。彼も、この冬に怪我をしてから実際には投げれていない。
自分がいなくても勝ち上がるチーム。必要とされていないんじゃないかという不安から、リハビリに身が入らなかった。目的も見失っていた。
しかし、あの瀬川陸という打者。
(投げてみたい)
久しぶりに、有は熱を感じていた。
治療帰り、鼻歌まで歌っていた大海に声をかけてよかった。
有は、その偶然に感謝しつつ、この夏までの復活を誓うのであった。

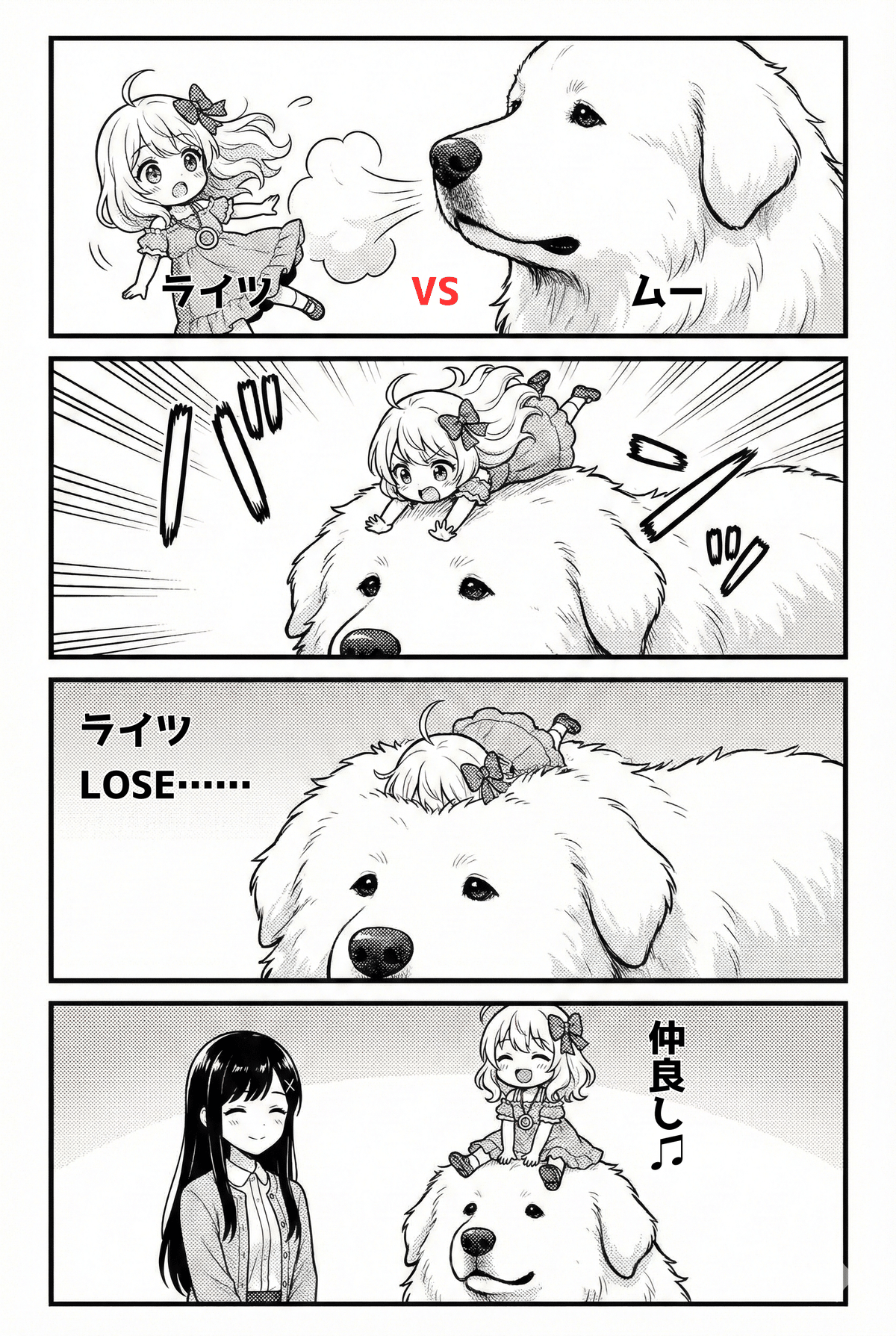

0 件のコメント:
コメントを投稿