彼女の右目に映るもの
「あなたの悪事、私の目が全て見通しよっ!」
指差した相手は見事に動揺していた。
あんなにうろたえてたら自分が犯人だって言ってるようなものじゃない?
でも、無理もないかな。
「な、何を言ってるの。黄色い目をしたお嬢さん」
そうそう目が怖いんだよね。でも、黄色いのは右目だけ……いや、片方だけの方が目立つのか。
「証拠はあるの?」
「えっと」
あれ、何だっけ。台詞忘れた。
「それはあの子が言ってたから」
口に出しかけて飲み込んだ。視界の片隅でブンブンと首を横に振っている彼の姿が目に入ったから。
あぁ、はいはい。これは禁句ね、分かってます。
「あなたが毒を捨てた場所。案内してあげるって言ったら、どう?」
あの慌てよう見てたら台詞を思い出せた。よかった、よかった。
「二十点」
意気揚々の私に彼は冷や水をぶっかけてきた。
「き、厳しい」
彼は夏だというのに、重っ苦しい真っ黒なスーツを着ていた。
「嬢ちゃん、芝居の癖が強すぎ。最後まで話せたのは奇跡だな」
う~、それは分かってる。私だって、私相手に話を聞こうとは思わないもん。怪しすぎる。
「でも、相手は最初から身構えていた。それは嬢ちゃんが地道に活動してきた成果だぜ」
「それが二十点分?」
彼は満足げに頷いているが、私は不満だ。それじゃあ、今日の分の点数は零点ということじゃない。
どうやら私の不満が伝わったようで、彼はにやりと笑う。
「嬢ちゃん、あそこで自分の秘密を喋ったら零点で終わらない。分かってるよな」
「分かってる」
本当かぁ、と彼は疑っている。確かに口を滑らせたのは私だけど、そんなに信用無いかなぁ。
――いいか、嬢ちゃん。その目は切り札(ジョーカー)だ。使う時は気をつけろ。下手に話すと敵をつくる。俺みたいな物好き、そうそういないからな。
優(ゆう)さん、あなたに言われたことなんだから覚えてるに決まってるじゃない。
事務所の扉を開けて、大げさにため息をついた。
「はぁ。遠かったなぁ。パパには反対されたけど、やっぱり免許取ろうかな」
「嬢ちゃんが、運転?」
「……そこ、驚くところ?」
私は、どんと勢いよく座り込んだ。その様子が淑女(レディ)らしくない、と彼がたしなめてくる。
正直、うるさい。
彼のことは無視しよう。聞こえないふりは慣れている。
無視する私相手に静かになった彼が、また話しかけてきた。
「それで、坊主には報告できたのか」
その話なら、してあげてもいい。……あげてもいいって、我ながら何様よね。
「あの子、私が見つけた時に、もう消えかけてたからなぁ」
あの子とは自殺に見せかけて殺された犠牲者。
「一応話したけど、私の声が届いたかどうか」
そして、有力な情報提供者だ。
私の右目だけが黄色いのは、生まれつきじゃない。幼い頃に高熱を出して、気がついたら黄金に染まっていたんだ。
そこからは地獄だった。何で、地獄かって?
想像してみて。
目が覚めて、最初に見る顔がママじゃなくて、ドロドロに顔の溶けたおじさんだったりしたら。正気でいられると思う?
私の右目は、この世にいないものを見ることができる。
あの子も私が会った時、すでに死んでいた。だから、事件解決しても無力感を感じてしまう。私のしていることは結局、自己満足じゃないのって。
「そう落ち込みなさんな」
そんな私の表情に気づいて、優さんが笑って声をかけてきた。
「嬢ちゃんが気づいて、皆の心に刻みつけた。それは価値がある」
彼に讃たたえられると悪い気はしない。しないけど、さっき低い点数をつけられたことを根に持っているので反撃しよう。
「優さん、真剣味がないのよ。だって、うさんくさいもの」
「なにを。こんな紳士をつかまえて、うさんくさいって」
「だったら、もっとすっきりとした服装に着替えなさいな」
俺には俺のポリシーがある、と叫んでいる。そのポリシー、何度も聞いてるんだって。私が毎回気になるのは、喪服もかねて、ってトコ。
「誰が相手か教えなさいよ、それなら」
小さく呟いた。
私はずっと、その相手を探し続けている。本人に聞ければ早いのに、それができないのがもどかしい。
でも、試してみようか。ふと、思い立って、優さんに向き合った。
「優さん、その嬢ちゃんっての止めてよ。私、いくつになったと思う?」
最初に会ってから何年経ったろう。
「嬢ちゃんが、一人前の淑女(レディ)になったら考えてやるよ」
それでも変わらない、嘘くさい笑顔を添えて彼は同じ返答を繰り返す。
「その時は、嬢ちゃんに似合う花でも買ってやるからさ」
ここだ。
激しくなった動悸に息が苦しくなる。全てが壊れそうで、言いたくない。
「花を買うって。そんな日、もう二度と来ないじゃない」
それでも私は、決定的な一言を言ってやった。
「ん、何か言ったか」
途端に脱力。やっぱりね。そうなると思った。
ふぅ、と大きく息を吐いて右目を右手で隠してみる。
瞬間、音が消えた。そして、そこにあった優さんの姿も消え去った。左目に映るのは、生活感のない殺風景な事務所の風景。
その空虚な空間を見ていると、不安でたまらなくなる。私は慌てて、右手をどかした。右目の視界が涙でぼやけたのは、きっと気のせいだ。
「どうした、嬢ちゃん」
優さんの姿を見て、安心した。
安心?
我ながら、矛盾している。彼がいなくなることを望んで、姿が無いと動揺するんだから。
そう、彼も、すでにこの世にいない。他の人と違って、存在がハッキリしすぎてるから時々忘れそうになるのだけれども。
――いいか、嬢ちゃん。
閉じた目に映るのはいつもの黒ではなく、一面の朱。
私を庇かばって刺された傷から、流れ出る鮮血。
パパにお願いして、彼の遺品を整理しようと事務所に訪れたとき、「よぉ、嬢ちゃん」と変わらぬ笑顔で出迎えてくれた時の驚きを、今も忘れることはできない。
あれから、私も大人と言える年齢になった。なのに、彼が消える気配がない。
長く留まりすぎて原型を無くし、悪意の塊かたまりになってしまった人を何度も見ている。そうなると、もう私ではどうにもできない。
だから、私は決めた。
この人が教えてくれた右目の使い方を駆使して、この人が抱えている無念が何なのか探って、バシッと解決して送り出してやるんだって。
まぁ、バシッとできる時が今のところ皆無だけど。
「嬢ちゃんは、まだまだ手がかかる」
子ども扱いする彼にはイラッとくる。でも、実際一人ではどうにもできないことが多い。
本当なら、優さんは自分で事件を解決したいはずだ。でも、私以外に話しかけても通じないもんだから、私を影から支えているつもりになってるらしい。
死者は存在に不都合な真実を、ねじ曲げる。それは知ってるけど、ずいぶんご都合主義じゃない?
そんなわけで、お化けの見える黄金の右目しか取り柄のない私と、その相棒を気取っている真っ黒な死者という奇妙な関係が誕生した。
行き先は不透明。
「まぁ、いいか」
長引きそうだけれど、仕方ない。これは私にとって、優さんへのお礼と、贖罪しょくざいだ。どれだけかかってもいい。
電話が鳴っている。
「はい、松木探偵事務所です」
看板は、彼の生前から変えていない。こうしていれば、優さん目当ての客がやってくる。
『……あれ、女の子?』
今回もそのようだ。きっと、これを繰り返していけば優さんの未練へとたどり着けるはず。
「私にお任せを!」
さて、今回は何を見ることになるのやら。まぁ、優さんと一緒なら大丈夫かな、とりあえず。

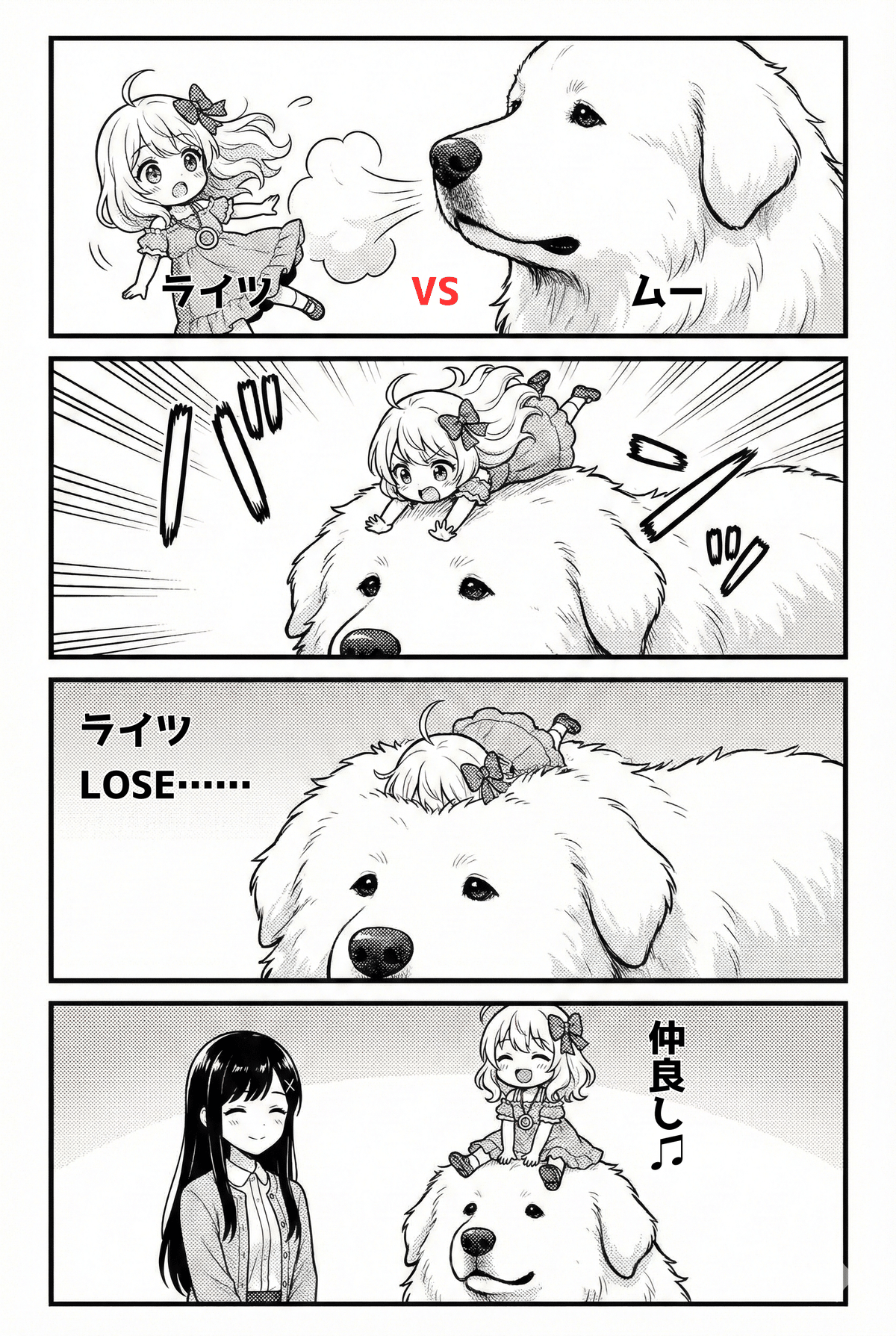

0 件のコメント:
コメントを投稿